犬も風邪を引くのかな? 人の風邪がうつってしまうことがあるのかな? など、疑問に思ったことはありませんか。人と同じように、犬にも発熱、鼻水、咳、くしゃみといった風邪のような症状を起こす病気があります。
目次
■犬の風邪「ケンネルコフ」を知ろう!

いわゆる犬の風邪とは、「犬伝染性気管気管支炎」という病気でケンネルコフとも言われます。ケンネル(犬舎)コフ(咳)という英語名の通り、犬舎など集団で飼育している所で多く発生が見られる病気です。伝染性の強い感染症なので、ペットショップ・動物病院・ペットホテルなど犬が多く集まる所で感染してしまうことがあります。
特に、免疫力の低い子犬がかかりやすく、ペットショップやブリーダーさんからお迎えしたばかりの子が自宅で咳をするようになり、動物病院を受診するというのは比較的よく聞くお話です。
■ケンネルコフはどんな症状が出るの?

基本的には人の風邪と似たような症状がでます。軽度の場合は、特に乾いたような咳がたくさん出ることが特徴です。それに伴って、微熱やさらさらとした鼻水を認めることもあります。症状が進行して重度になってくると高熱が出たり、痰が絡んだような咳に変化したり、色のついた鼻水や目やにを認めたりするようになります。
軽度なうちは元気がなくなったり食欲が落ちたりすることはあまり見られませんが、重度になってくるとぐったりしてごはんも食べられなくなってしまう子もいます。肺炎に進行してしまうこともあり、治療を受けないと死に至ることもあります。
■原因は?人にも感染するの?

ケンネルコフの原因は、数種類のウイルスと細菌が単独もしくは複数感染することにより引き起こされます。咳やくしゃみなどで空気中に飛び散った病原体を吸い込んでしまったり、ケンネルコフにかかっている犬と直接接触をしたり、汚染された環境下で犬から犬に感染流行してしまいます。
人の風邪の場合、90%はウイルス感染が原因と言われています。例外もありますが、基本的に人のウイルスは人にだけ、犬のウイルスは犬にだけ感染しますので、基本的に愛犬がケンネルコフにかかったからといって人に感染してしまうことはありません。
■どんな治療法があるの?

一般的に軽度の場合はお薬を使わず、自宅でゆっくりと休ませ栄養をとることで改善することが多いです。症状が強く出ている場合は、お薬による治療が必要となってきます。
症状にもよりますが、痰を出しやすくし気管支の炎症を和らげる目的で気管支を拡げるお薬や、痰を出しやすくするお薬、細菌感染に対して抗生剤を使用することもあります。あまりに咳がひどく夜も眠れないような場合は、一時的に咳を止めるお薬を使用することもありますが、痰を出すことが出来なくなってしまうので気を付けて使用しなくてはいけません。ネブライザー療法と言う方法で、このようなお薬を霧状にして吸引させる方法も効果が認められています。
■ケンネルコフを予防することはできる?

ケンネルコフの原因として知られている病原体の一部は、ワクチンで予防することができます。
接種のタイミングや免疫などで、ワクチンさえ打っていれば完全に予防できるというわけではありませんが、万が一感染しても軽度で済んだり、しっかりと免疫がついていれば感染を防ぐことができたりしますのでおすすめです。
■自宅でのケア方法や予防法は?

・栄養をつけて休ませる
人の風邪と同じようにフードなどで栄養をつけてあげて、ゆっくりと休ませてあげることが一番の治療法になります。水分補給も大事なので、水をあまり飲まない子にはウェットフードを与えることもよいでしょう。
・部屋を清潔にする
環境をきれいに保つことも重要です。愛犬の居室は、空気の入れ換えやおそうじなどをこまめにしてあげましょう。また、お部屋の湿度や温度にも気をつけてあげましょう。体が冷えると免疫力が下がってしまうと言われています。人が快適な温度に室温を保ち、温かい寝床も用意してあげるといいでしょう。
・同居犬への配慮も怠らない
何頭か犬を飼っている場合は、同居の子に感染してしまうことを防ぐために隔離をすることがおすすめです。ケンネルコフになっている子のお世話をした後は、感染を広げないために手洗いをしっかりするようにしましょう。
シニア犬は抵抗力が落ちていることもありますので、もし新しい子犬を迎える予定がある場合はワクチン接種歴を確認し、かかりつけの獣医さんと相談してお迎えの前にきちんと免疫をつけておいてあげることもおすすめです。
ただの風邪だと飼い主さん自身で自宅療養の判断をせず、きちんと症状を見てあげましょう。呼吸が苦しそうだったり、舌がきれいなピンク色でなかったりする場合、ぐったりしてしまったり食欲が落ちていたりする場合は緊急の可能性もあるので、すぐに動物病院を受診しましょう。
ケンネルコフは珍しい病気ではありませんが、重症化すると死に至ることもあります。特にお迎えしたばかりの子犬でみられることが多く、症状がひどくなってしまうと命の危険もあります。ご自宅で愛犬の様子をしっかりとみてあげて少しでも心配なことがあればかかりつけの獣医師さんに相談しましょう。
※ 本サイトにおける獣医師および各専門家による情報提供は、診断行為や治療に代わるものではなく、正確性や有効性を保証するものでもありません。また、獣医学の進歩により、常に最新の情報とは限りません。個別の症状について診断・治療を求める場合は、獣医師や各専門家より適切な診断と治療を受けてください。
【関連記事】
※ 子犬や老犬がなりやすい?犬風邪と飛ばれる「ケンネルコフ症候群」とは
※ 冬の乾燥…犬にベストな湿度は何%?犬に配慮した加湿器の使い方
※ 季節の変わり目の体調管理!犬猫が秋に気をつけたい室温管理と花粉症について
【参考】
【画像】
※ Javier Brosch,Igor Normann,Anake Seenadee,tsik,135pixels, rodimov,didesign021 / Shutterstock
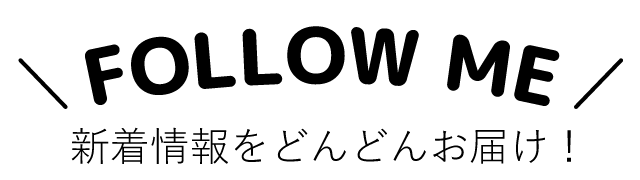












戻る
みんなのコメント